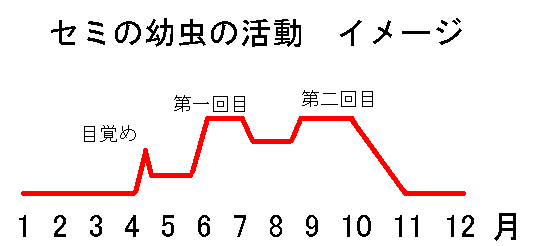飼育で羽化したセミ
アロエ/ユッカから羽化したセミ 1981〜2017年
ほとんどアロエから、ニイニイゼミはおもにユッカから羽化。
| セミの種類 |
幼虫期間 |
雄 |
雌 |
合計 |
備考 |
| ツクツクボウシ |
1年
2年 |
79
68 |
93
67 |
172
135 |
掛け合わせ実験を含む |
| ニイニイゼミ |
3年
4年
5年 |
19
44
5 |
12
27
3 |
31
71
8 |
奄美大島産を含む |
| ミンミンゼミ |
2年
3年
4年
5年 |
3
37
15
1 |
3
23
13
1 |
6
60
28
2 |
一冬のみ保温1雄2雌を含む
一冬のみ保温2雌を含む
.
. |
| アブラゼミ |
2年
3年
4年
5年 |
0
4
3
2 |
1
5
3
0 |
1
9
6
2 |
|
| クロイワツクツク |
2年
3年
4年 |
47
24
3 |
34
14
2 |
81
38
5 |
冬季保温5雄5雌を含む
.
屋久島産のみ |
| クマゼミ |
2年
4年
5年 |
1
5
3 |
0
8
4 |
1
13
7 |
一冬のみ保温
.
. |
| クロイワニイニイ |
5年 |
0 |
1 |
1 |
|
| リュウキュウアブラゼミ |
3年 |
1 |
0 |
1 |
|
オオシマゼミ |
2年
3年
4年 |
8
16
0 |
3
11
1 |
11
27
1 |
|
スジアカクマゼミ |
3年 |
0 |
1 |
1 |
|
| |
合計 |
381 |
337 |
718 |
|
温帯のセミの幼虫期間は例外的なツクツクボウシを除くと、卵の孵化時期、年2回発育パターン、終齢幼虫は一夏やり過ごすの三つの要素でだいたい決まる。セミの幼虫は6月頃と9月頃を中心に発育している。この年2回発育パターンがセミの生活史の骨格を成している。卵の孵化時期や成虫の出現期も年2回発育パターンの延長線上にあると考えられる。6月と9月は天気が悪いので、前後にずらし、多くのセミが7、8月に羽化している。夏の長い南西諸島では全体に間延びしてしまい、8月頃セミが少なくなる。
アブラゼミ、ミンミンゼミは産卵の翌年の第一回目の活動期にあたる6月下旬から7月にかけて孵化、第二回目の活動期にあたる8月末から9月にかけて、2〜3齢になり、翌年6月に2齢が3齢、3齢が4齢に、9月に3齢が4齢、早いものは4齢が終齢なるものがででくるが、終齢幼虫はひと夏やすごすので、翌年羽化せず、翌々年幼虫期間満3年で羽化する。多くの個体が終齢になるのは孵化から満2年後の6月で翌年3年で羽化するが、まれに8月頃羽化するのがいて、これが幼虫期間2年となる。終齢になるのが9月になると幼虫期間は4年となり、最長は5年である。ツクツクボウシは卵の孵化から、翌年の6月まではアブラゼミ、ミンミンゼミと同じように成長するが、6月4齢になったものは7月に終齢、8月後半から幼虫期間1年で羽化、8月頃終齢になったものは翌年幼虫期間2年で羽化する。ツクツクボウシは普通8月後半に最盛期になるので、自然状態でも幼虫期間1年のものが多いことを表している。また、ツクツクボウシの幼虫期間2年までしかないので、北日本での分布は夏場気温が上がる場所に限られてしまう。ニイニイゼミは産卵した年の9月頃孵化し、ほとんど1齢、わずかに成長の早いのが2齢で越冬、翌年6月に1齢が2齢に2齢が3齢に、9月に2齢が3齢、3齢が4齢、翌々年の6月には3齢が4齢、4齢は終齢になり、多くの個体が終齢になるのは孵化から満2年後の9月で、早いのは幼虫期間3年で羽化、多くは4年、遅いには5年で羽化する。クマゼミは卵の孵化が、茨城あたりでは産卵した翌年の8月中旬以降になり、ニイニイゼミの孵化時期に近いため、幼虫期間もほぼ同じになる。幼虫期間3年がないのは大きさのせいと考えられる。ニイニイゼミ、ミンミンゼミが羽化の準備を始めるのは6月に入ってからで、6月下旬には羽化できる状態になる。ニイニイゼミはまもなく羽化するが、ミンミンゼミは数週間から一月以上待機した後羽化する。